炭疽病
病害
病原菌
Colletotrichum cereale(旧Colletotrichum graminicola)
芝種
寒地型芝草全般に発生します。スズメノカタビラとクリーピングベントグラスが物理的なストレスを受けている時は特に感染しやすいです。
病徴
炭疽病は暖かくなると発生し、病原菌の感染する場所によって2タイプの炭疽病(葉枯タイプと株腐タイプ)に分かれます。
葉枯タイプの病原菌の主な感染場所は葉です。一般的に新葉での初期感染は少なく、葉齢の進んだ下葉において初期感染が観察されます。病気は下葉の先端から株元へ向かって進展し、黄色から茶色の不定形パッチを形成します。葉には、中央が黒く、全体が黄色い病斑が現れることもあります。気候の暑い時期には病徴がより深刻なため、葉全体が一気に枯れます。
株腐タイプは病原菌の主な感染場所が地際部のものを指します。地際部に感染し腐敗させるため、地上部は簡単に抜けるようになります。激しい場合は芽数が少なくなります。葉枯タイプよりも株腐タイプの方が治療・回復に時間を要します。
枯れた葉や茎は、分生子層と呼ばれるトゲのある小さくて黒い器官に覆われます。これを確認するためにはルーペが必要です。

葉枯タイプパッチ

株腐タイプパッチ

分生子層
病原菌の生態
炭疽病菌は寄生と腐生をする能力に優れた菌です。これは長期間サッチや土壌で生息することが可能で、植物へ感染するチャンスを伺えることを意味します。冬期間はサッチや植物体で過ごし、暖かくなると分生子が風や水によって広がり新たに感染します。発病させる力は弱く、ストレスの罹った植物のみを犯します。
発生環境
炭疽病は気温15℃を超えるようになると発生します。この病害は葉面が湿った状態が一日に10時間以上続き、しかもこのような日が数日連続するエリアで発生します。また、土壌のコンパクション、過湿・過乾燥(ドライスポットなど)、低い刈高、低い窒素レベル、虫害、他の病原菌によってもこの病害が進行します。若い植物体よりも老齢の植物体に感染・発病しやすいです。
管理のコツ
- 刈高を高くします
- 歩行式のモアを使用して、ストレスを最小限にします
- 出来るだけその部分のトラフィック(歩くまたは機械が通る事)を減らします
- 極端に厚い目砂の施用は控えるようにします
- 十分な窒素量と養分バランスのとれた土壌を維持します
- 芝が萎えないように十分な散水を行います
- この病徴が出ている期間のコア抜きなどの更新作業をしないようにします
- 秋にコア抜きとインターシーディングを実施します
- フェアウェイのカタビラを減らして炭疽病に強い栽培品種を播種します
- 病害が慢性化した場所では予防的に殺菌剤を散布します
- 殺菌剤により病原菌の活性を止めた後、肥料により芽数を上げます
発生時期
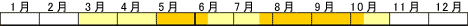
発生時期の表記について
■ :多発生 ■ :発生
最近の話題
- 最近は早春からの発生が早まっている傾向にあります。特に積雪地帯では融雪直後に発病する例もあります。
- 一見ドライスポットに見える場合でも、根を確かめてみると濡れていることがあります。虫害の場合もありますが、炭疽病の場合もあります。
- 株腐タイプの炭疽病が増えており、回復がしづらいことから問題となっています。またピシウムとの複合感染により、炭疽病に卓効を示す薬剤の効果が現れにくいことがあります。


シンジェンタからのお奨め防除法
- いったん炭疽病が発生すると回復が難しいことが多いです。殺菌剤は炭疽病菌の勢いを止めるだけで、芝の治療・回復は見込めません。病勢が治まった時に適切な肥培管理で治療・回復をしましょう。
- 炭疽病は老化病やストレス病とも呼ばれます。インターシーディングを行うことで新しい植物体の密度を高め、発病させにくくする方法も有効です。
- 炭疽病で困っているコースは窒素量が低い場合が多いです。そのコースに加わるストレスを吟味して窒素が少なくならないようにすることが必要です。
- 株腐タイプの炭疽病は薬剤が到達しにくい位置に菌が感染する病気です。極端な少水量薬剤散布は適さない場面が多いと思われます。
- 炭疽病に効果的な殺菌剤はバナーマックスを始めとするトリアゾール系の薬剤です。近年炭疽病の発生が長引いているため、計画的な薬剤ローテーションを必要とされるコースが増えています。カシマンなどのグアザチン系薬剤やベンゾイミダゾール系の薬剤が炭疽病のローテーション剤として挙げられます。

