立枯病 (ゾイシアデクライン)
病害
病原菌
Phialophora sp.
芝種
ノシバ、コウライシバ
病徴
春期にノシバ・コウライシバの萌芽が揃わない、もしくは秋期にパッチ状に枯れてくる場合、ゾイシアデクラインの可能性が考えられます。パッチは直径5-30cm程度で輪郭が明確でないことが多く、下葉から徐々に枯れてきます。また、罹病した芝生は根部や匍匐茎の生育が著しく悪くなるため、病害からの回復が遅れる傾向にあります。一般に温度の上昇と共に病徴は軽くなる傾向にありますが、激発時には夏期・冬期にもパッチが目立つことがあります。

コウライグリーンに早春に発生したパッチ

コウライグリーンにおける初発の様子

コウライフェアウェイにおける発生
病原菌の生態
黄化しかかっている下葉の地際部に特徴のある菌糸を形成します。発病が観察されない時期にも健全な植物から観察されることも多いため、年間を通じて植物に感染していることが予測されます。
茶褐色で裂片状の菌足(矢印)をもつことが特徴


発生環境
ゾイシアデクラインは、砂質土壌のグリーン、ティーおよびフェアウェイにおいて発生が多い傾向です。なかでもマウンド・風の吹き抜ける所など、乾燥しやすい場所で激しく発生します。また歩経路になる場所、常に機械の通り道となる所などのストレスが加わりやすい場所にも発生しやすく、回復も遅れることが多いです。これは芝の根・匍匐茎の発達が悪いこととも関係があるのかもしれません。
雨の日にはパッチは赤味を増すため目立つ。水がたまる低地には発生がなく水はけの良いマウンドに発生しやすい。

管理のコツ
- 乾燥条件を避け水持ちをよくするため、目砂をやめて目土をします。
- ゾイシアデクライン菌は乾燥条件を好むと思われるので冬期に乾燥している時は散水を行います。
- ゾイシアデクラインが発生する場所では根・匍匐茎の発達が悪いことが多いため、健全な根・匍匐茎を作ることに努めます。
- 特に細葉コウライシバで発生が多いため、やや葉幅の広い品種に切り替えます。
- 予防目的に浸透性殺菌剤を散布します。
発生時期
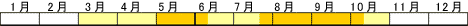
発生時期の表記について
■ :多発生 ■ :発生
シンジェンタからのお奨め防除法
- ゾイシアデクラインに対する登録薬剤にはヘリテージ、センチネル、シバンバ、シバンバPROがあります。発病後の散布は効果が劣るため、予防散布が効果的であることが分かっています。春発生のゾイシアデクラインに対しては秋の予防散布が効果的です。
- ゾイシアデクライン以外にも類似した症状を起こすものとして疑似葉腐病(春はげ症)、コウライシバのダラースポット、コウライシバの炭疽病などがあります。なんとなくモヤモヤと発生している症状の原因を調べることが重要です。
疑似葉腐病(春はげ症)は顕微鏡で観察し、2核リゾクトニアの細い菌糸を確かめることによって判定します。


コウライシバのダラースポットは早朝に菌糸が浮くことが判別のポイントです。


コウライシバの炭疽病の分生胞子層は20倍程度のルーペで観察が可能です。
枯死葉には病気と無関係に頻繁に観察されますので注意が必要です。
枯れかかっている葉で観察されることが多い場合、炭疽病であることが疑われます。



